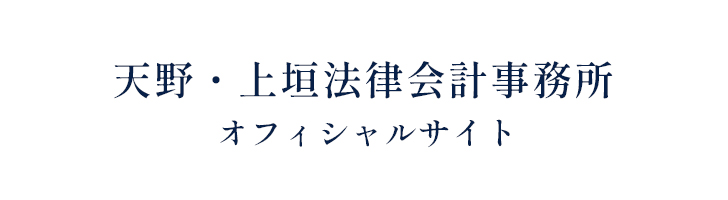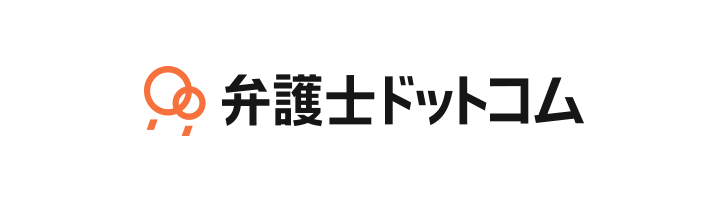- HOME>
- むち打ちでも後遺障害等級に認定されるのか
交通事故でむち打ちになり、治療を続けても症状が改善せず後遺症が残る場合、後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
むち打ちは外見から症状が分かりにくいため、医療機関での適切な診断や治療経過の記録が非常に重要です。
これからむち打ちで後遺障害等級が認定される基準やその手続きについて解説します。
むち打ちとは?
むち打ちは、交通事故などで首に過度な負担がかかった際に発生しやすい障害です。
「頚椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」と診断されることが多く、次のような症状が一般的です。
- 首や肩の痛み
- 手足のしびれ
- 頭痛やめまい
- 吐き気や耳鳴り
通常、治療期間は約3か月程度とされていますが、症状が長引くこともあり、場合によっては後遺症として認定されるケースもあります。
後遺障害等級認定の重要性
むち打ちで後遺障害等級が認定されることで、被害者にはいくつかの重要な権利が生じます。
後遺障害慰謝料の請求
後遺障害等級が認定されると、精神的苦痛に対する補償として「後遺障害慰謝料」を請求できます。
例えば、14級の場合の慰謝料は弁護士基準で約110万円、12級の場合は約290万円が相場です。
逸失利益の請求
むち打ちによる後遺症で労働能力が低下した場合、生涯収入が減少する可能性があります。
その損失を補うのが「逸失利益」です。
14級では約70万円~150万円、12級では約350万円~800万円の補償が見込まれます。
賠償金の一部を早期に受け取れる
後遺障害等級が認定されると、相手方の自賠責保険から一部の賠償金を先に受け取ることが可能です。
被害者請求という手続きを通じて、12級なら最大224万円、14級なら最大75万円の支給を受けることができます。
むち打ちで認定されやすい後遺障害等級

むち打ちの後遺障害等級は、主に14級または12級に該当します。
それぞれの基準と条件は以下の通りです。
14級:局部に神経症状を残すもの
14級9号は、むち打ちの症状が医学的に「説明可能」であれば認定される等級です。
たとえば、画像診断では異常が確認できなくても、交通事故後の症状が一貫して継続している場合には認定される可能性があります。
12級:局部に頑固な神経症状を残すもの
12級13号は、MRIやCTスキャンなどの画像検査で、神経根の圧迫やその他の異常が確認される場合に認定されます。
この等級では、14級よりも重い障害があることが前提となります。
後遺障害認定を受けるためのポイント
むち打ちで後遺障害等級を認定されるには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
事故の状況と治療経過の記録が重要
事故の状況や損傷の程度が、後遺障害認定の基準に合致していることを証明する必要があります。
また、治療期間の長さや通院頻度も認定において大きな判断材料となります。
症状の一貫性と医学的な証明
症状が事故直後から症状固定まで一貫して続いていることを示すことが重要です。
特に、医師に適切に説明し、診断書に記載してもらうことが求められます。
また、MRIや神経学的検査などで症状の客観的な証明を行うことが、認定の成功率を高めます。
定期的な通院が必要
通院頻度が少ない、または治療が途中で中断してしまうと、後遺症の継続性が疑われる可能性があります。
一般的には、6か月以上の継続的な通院が認定のために推奨されています。
後遺障害認定の手続きと注意点
後遺障害等級認定は、医師から「症状固定」と診断された後に行います。
手続きには以下の2つの方法があります。
被害者請求
被害者が直接、相手方の自賠責保険に申請する方法です。
この方法では、被害者自身が必要な書類を揃える手間がありますが、被害者に有利な資料を提出できるというメリットがあります。
事前認定
相手方の任意保険会社を通じて申請する方法です。
手続きが簡単ですが、保険会社が被害者に不利な資料を提出する可能性があり、結果的に不利な認定結果となる場合もあります。
どちらの方法を選ぶにしても、診断書の記載内容や証拠書類が不十分であれば、適正な認定を受けられない可能性があります。
弁護士に相談する重要性
むち打ちの後遺障害等級認定は、認定基準の解釈や手続きが難しいため、交通事故に詳しい弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士は次のようなサポートを提供します。
- 医師への適切な伝え方や診断書作成のアドバイス
- 必要書類の収集や申請手続きの代行
- 事故後の通院方法や検査内容のアドバイス
- 認定後の慰謝料や逸失利益を巡る示談交渉
弁護士に相談することで、認定の可能性を高めるだけでなく、その後の補償額を最大限に引き出すことができます。